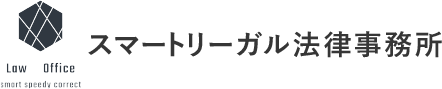2025/10/25 相続
【Q&A形式で解説】遺産が宙に浮く!?「相続財産管理人」が選任されるのはどんな時?
はじめに
「相続人がいない」「相続人全員が相続放棄をした」…。亡くなった方の財産(遺産)の行方が分からなくなり、管理・清算が必要になるケースがあります。そんな時に登場するのが「相続財産管理人」(法改正後は相続財産清算人)です。
今回は、相続の専門家である弁護士が、選任される条件や手続きについて詳しくお伝えします。

弁護士が解説!「相続財産管理人」の選任とは
Q1. 相続財産管理人(清算人)は、どのような目的で選任されるのですか?
弁護士: 主な目的は、「相続人のあることが明らかでないとき」に、故人の残した財産を管理・清算し、最終的に国庫に帰属させるための手続きを進めることです。
少し専門的になりますが、民法の改正(令和5年4月1日施行)により、現在は「相続財産清算人」という名称に変わっています。役割としては、故人の債務を弁済したり、財産を換価したりして、きちんと清算する役割を担います。
Q2. 「相続人のあることが明らかでないとき」とは、具体的にどんな場合ですか?
弁護士: 以下の3つのケースが典型的な事例です。
-
戸籍上、法定相続人が存在しない場合: そもそも戸籍を辿っても、配偶者、子、両親、兄弟姉妹といった法定相続人が誰も見つからない場合です。
-
全員が相続放棄をした場合: 最初の相続人(例えば配偶者と子)が全員相続放棄をし、次の順位の相続人も全員が放棄するなど、結果的に相続する人が誰もいなくなった場合です。
-
相続欠格・廃除など: 相続人がいたとしても、「相続欠格」(重大な非行などによる相続権の剥奪)や「推定相続人の廃除」などによって、相続権を失い、誰もいなくなってしまった場合です。
また、相続人はいるが、遺言によって財産の一部だけが第三者に「遺贈」された場合(部分的包括遺贈)も、清算手続きが必要になるため、選任事由となり得ます。
Q3. 相続人がいるかどうか確定していない場合でも、選任できるのでしょうか?
弁護士: はい、実務上は認められることがあります。例えば、認知の訴えなど、誰が相続人になるかを裁判で争っている最中で、相続人が未確定の状態でも、財産の腐敗を防ぐ必要があるなどの理由があれば、選任の申立てが可能です。
ただし、その場合は、判決が確定するまで財産の本格的な清算手続き(債務の弁済など)は行われないのが一般的です。
Q4. 相続財産清算人が選任されるのは、「相続人がいない場合」だけですか?
弁護士: いいえ、他にもいくつかの選任事由があります。清算とは別の目的で選任されるケースです。
-
相続財産の保存: 相続財産清算人がまだ選任されていない場合に、遺産が散逸したり、腐敗したりするのを防ぐために、単に「保存」を目的として管理人の選任が申し立てられることがあります。
-
限定承認: 相続人が、被相続人の債務を財産の範囲内でのみ承継する「限定承認」を選択した場合、相続人の中から特定の1名を相続財産管理人として選任し、清算手続きを進めることがあります。
Q5. 誰が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求できるのですか?
弁護士: 申立権者は、「利害関係人」または「検察官」に限定されています。
「利害関係人」とは、相続財産について法律上の利害関係を有する者で、具体的な例としては以下の人々が該当します。
-
相続債権者、受遺者: 故人にお金を貸していた人や、遺言で財産を受け取ることになっていた人。
-
特定の不動産取得者: 故人から不動産などを購入したが、登記が未了のままになっている人。
-
地方自治体: 固定資産税などの租税債権を有する、または空き家対策で費用を回収する必要がある地方自治体。
-
管理組合: マンションの管理費や修繕積立金の債権を有する管理組合も利害関係人になります。
Q6. 請求すれば必ず選任されるのでしょうか?
弁護士: 必ずしもそうではありません。家庭裁判所は、選任の必要性を厳格に判断します。
代表的な却下ケースは、「管理費用を賄えるだけの相続財産が存在しない場合」です。弁護士報酬や裁判所への予納金が遺産から支払えないと見込まれる場合は、申立てが却下されます。
ただし、訴訟を提起する必要があるなど、特に選任の必要性が高いと裁判所が判断すれば、財産が少額であっても選任されることもあります。
相続についての相談をしたい方はスマートリーガル法律事務所のLINEから。