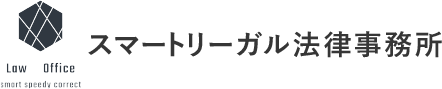2025/10/05 労務問題
【製造業の経営者・工場長様へ】問題社員の解雇、その前に。弁護士が教える安全と品質を守る普通解雇の進め方
「熟練工は高齢化し、若手は育たない。そんな中、たった一人の従業員のミスが、ライン全体を止め、重大な事故を引き起こしかねない…」
製造業の経営者や管理者の皆様は、日々このような厳しい現実と向き合っておられることと存じます。技能伝承という長期的な課題を抱えながら、目先の安全管理と品質維持という絶対的な使命を果たさなければならない。このジレンマが、製造業における労務管理を特に難しくしています。
能力不足や安全意識の低い従業員への最終手段として「普通解雇」を検討する際、その判断と手続きを誤れば、「不当解雇」として法的な紛争に発展し、企業の存続を揺るがす可能性があります。
本記事では、スマートリーガル法律事務所が、製造業の特殊性を踏まえ、問題社員への対応から普通解雇に至るまでの、法的に正しく、かつ実践的な手順を「4つのステップ」で解説します。

なぜ製造業の解雇は難しいのか?法的な大原則
まず大前提として、日本の法律では、会社が一方的に従業員を解雇することは厳しく制限されています。解雇が有効と認められるには、「客観的に合理的な理由」があり、かつその解雇という処分が社会の常識に照らして妥当である「社会通念上の相当性」が必要不可欠です 1。
これを証明する責任は、すべて会社(工場)側にあります。特に、技能伝承が課題である製造業において、安易に「能力不足」を理由に解雇することは、「企業の教育不足」と判断されかねません 2。
解雇を検討する前に踏むべき「4つのステップ」
トラブルを避け、万が一の際に会社の正当性を主張するためには、解雇という最終判断に至る前に、以下の段階的なプロセスを丁寧に踏むことが極めて重要です。
STEP 1: 客観的な証拠を集める – 「印象」を「事実」に変える
「仕事が遅い」「やる気がない」といった管理者の主観的な評価だけでは、法的な解雇理由として認められません 3。必要なのは、誰が見ても納得できる客観的なデータと事実の記録です。
【製造業で収集・作成すべき証拠の例】
- 生産性に関する定量的データ: 生産管理システムから、対象従業員の生産数やサイクルタイムを抽出し、他の従業員の平均値と比較した記録 4。
- 品質に関する定量的データ: 品質管理(QC)部門の記録に基づき、当該従業員が担当した工程での不良品率や手直し件数をまとめたデータ 5。
- 安全・規律違反に関する記録: ヒヤリハット報告書や事故報告書、安全規則違反(保護具の不着用など)に対する指導書や警告書の写し 6。
- 業務日報や指導記録: 上長が記載した指導内容や、面談時の従業員の反応を記録したメモ 7。
STEP 2: 改善の機会を与え、記録する – 「解雇回避努力」の実行
証拠を集めたら、次は改善の機会を与えます。これは、従業員のためであると同時に、会社が「解雇を回避するために努力した」ことを示すための、法律上極めて重要なステップです 8。
- 段階的な指導を行う:
まず口頭で具体的な問題点を指摘し、改善を促します。それでも改善が見られない場合は、書面で「注意書」や「警告書」を交付し、事態の重大さを伝えます 9。 - 業績改善計画(PIP)を策定する:
「不良品率を現在の10%からライン平均の2%まで低減させる」といった、具体的で測定可能な目標を設定します 10。その達成のために「熟練工によるOJTを週4時間受講する」といった行動計画も明記し、本人と共有します 11。 - OJTや研修の記録化:
「実施した」だけでは不十分です。「いつ、誰が、誰に、何を教え、その結果どうだったか」を記録した
OJTログを作成することが、会社の教育責任を果たしたことの証明となります 12。
STEP 3: 解雇以外の選択肢を検討する – 「最後の手段」であることの証明
指導を重ねても改善しない場合でも、すぐに解雇通知を出すのは早計です。その前に、解雇以外の方法で雇用を維持できないかを検討する義務があります 13。
- 配置転換(配転)を真剣に検討する:
過去の裁判例でも、会社が配置転換などの解雇回避努力を尽くさなかったことが、解雇を無効と判断する大きな理由となっています 14。
- 【検討例】: 精密作業が求められるラインから、比較的単純な検品や梱包、倉庫管理の部門へ。
- たとえ工場内に適切な異動先がない場合でも、「
配置転換の可能性を真摯に検討したが、適当なポジションがなかった」というプロセスとその記録を残すことが、解雇がやむを得ない最終手段であったことを示す上で重要になります 15。
- 検討した事実を記録に残す:
本人と公式な面談を設定し、代替職務を提示します。本人が拒否した場合は、その理由も含めて詳細な議事録を作成しておくことが、後の紛争で会社の立場を著しく強化します 16。
STEP 4: 最終手段としての手続き
上記のステップを全て踏んでもなお問題が解決せず、やむを得ず解雇に踏み切る場合には、法に定められた手続きを厳格に遵守する必要があります。
- 退職勧奨の実施(任意): 解雇の前に、退職金の割り増しなどの有利な条件を提示し、合意による円満な退職を促す「退職勧奨」を検討することも有効な選択肢です 17。ただし、あくまで任意であり、強要してはなりません 18。
- 解oco通知の交付: 解雇日の30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います 19。その際、就業規則のどの条項に基づき、どのような具体的な事実(STEP 1で収集した証拠に基づく)が解雇理由に該当するのかを明確に記載した「解雇理由証明書」を準備しておくことが重要です 20。
まとめ:安全と品質は、健全な労務管理から生まれる
製造業における普通解雇は、技能伝承、安全、品質という事業の根幹に関わる問題です。解雇が無効か有効かの分かれ目は、**「企業がどれだけ誠実に、客観的なデータに基づいて改善の機会を提供し、解雇を回避する努力を尽くしたか」**というプロセスにあると言っても過言ではありません。
問題が発生してから対処するのではなく、採用段階でのミスマッチ防止や、日々の指導・評価を記録する文化の醸成といった「予防法務」こそが、最強のリスク管理です。
しかし、個別の事案はそれぞれ複雑であり、自己判断は危険を伴います。対応に悩んだら、できるだけ早い段階で、私たちスマートリーガル法律事務所のような労働問題に精通した弁護士にご相談ください。それが、工場の安全と品質、そして会社を守るための、最も確実な解決への近道です。