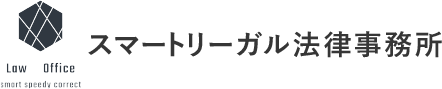2025/07/01 労務問題
【保存版】建設現場の問題社員、普通解雇で対応する際の完全ロードマップ
「何度注意しても安全意識が低い…」
「現場のチームワークを乱してばかりで、工期にも影響が出そうだ…」
「基本的な技能が身につかず、任せられる仕事がない…」
建設業界は、深刻な人材不足という課題を抱える一方で、現場の安全と品質を確保するため、従業員一人ひとりに高い能力と規律が求められます。このような状況で「問題社員」への対応に頭を悩ませる経営者や現場責任者の方は少なくないでしょう。
最終手段として「普通解雇」を考えざるを得ない場面もあるかもしれません。しかし、日本の法律では従業員の解雇は厳しく制限されており、安易な判断は「不当解雇」として訴訟に発展し、企業に大きなダメージを与える可能性があります 。
本記事では、弁護士が建設業界の特性を踏まえ、問題社員への対応から普通解雇に至るまでの正しい手順を「5つのステップ」で解説する、実践的なロードマップをご提供します。

STEP 0: はじめに – なぜ解雇は難しいのか?
まず、大前提として、会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの非常に厳しい条件をクリアする必要があります(労働契約法第16条)。これは、解雇という手段が、誰が見ても納得でき、かつ「やりすぎ」ではないと判断されなければならない、ということです。
特に建設業では、
- 深刻な人材不足:貴重な人材を失うことやパワハラ指摘の懸念 から適切な指導がでてきていない。
- ルールが不明確:暗黙の了解で様々なルールが運用されているケースが多い
- 現場ごとの環境変化:場所によって従業員のパフォーマンスが変わる可能性 。
といった特殊な事情が絡み合い、解雇の判断はより一層難しくなります 。このロードマップは、そうした複雑な状況の中で、企業が踏むべき手順を明確にするためのものです。
STEP 1: 問題の可視化 – 「なんとなく」を「客観的な事実」に変える
ロードマップの第一歩は、問題点を客観的な事実として記録することです。「あいつはダメだ」という主観的な評価ではなく、具体的な「いつ、どこで、何をした」という事実を積み重ねることが、すべての基本となります。
【建設業で問題となりがちな解雇理由の具体例】
- 能力不足・成績不良
- 例: 指導しても基本的な図面が読めず、手戻り工事が頻発する。安全に関わる重要な指示を理解できない。複数回、詳細な指導を行っても、与えた業務を十分に遂行できない。
- 協調性の欠如
- 例: 他の作業員への暴言や非協力的な態度で、現場のチームワークを著しく乱す。元請けや他業者とトラブルを起こし、工事の進行に支障をきたす。
- 勤務態度の不良
- 例: 正当な理由なく遅刻や無断欠勤を繰り返し、朝礼や工程会議に参加しない。現場監督の正当な業務指示に反抗し、従わない。
- 安全意識の欠如
- 例: 高所作業で安全帯の不使用を繰り返すなど、安全規則を軽視し、本人や周囲を危険に晒す。
これらの問題行動があった際は、
必ず日時、場所、具体的な内容、指導内容、本人の反応(発言内容)などを記録しておきましょう。作業日報やヒヤリハット報告書なども重要な証拠となります。
STEP 2: 改善の機会提供 – 指導・教育という会社の義務
問題点を記録したら、次は改善の機会を与えます。いきなり解雇することはできません。従業員を育成し、改善を促すことは、法律上、会社に求められる「解雇回避努力」の重要な一環です。
- 段階的な指導・警告を行う
- まずは
口頭で具体的な問題点を指摘し、改善を促します。
- それでも改善が見られない場合は、
書面で「注意書」や「警告書」を交付し、事態の重大さを認識させます。書面には、改善すべき点、改善期限、そして「このままでは雇用契約の継続が難しくなる」可能性を明記します。
- 具体的な教育・研修の機会を提供する
- OJT(現場教育): 経験豊富な先輩や職長がマンツーマンで指導する機会を設ける。
- 研修参加: 安全教育や専門技術に関する社外研修に参加させる。
- 資格取得支援: 業務に必要な資格の取得をサポートする。
これらの指導・教育を行った事実も、すべて記録として残しておくことが極めて重要です。
STEP 3: 最終手段の検討 – 配置転換と退職勧奨
十分な指導・教育を行っても改善が見られない場合、解雇の前に、さらに検討すべきステップがあります。
- 配置転換・職務変更の検討
- 「現在の現場や業務が合わないだけかもしれない。この従業員が生きる場所を探そう。」という視点を持ち、他の部署や別の現場、あるいは本人の適性や健康状態を考慮した内勤業務への配置転換が可能かどうかを真剣に検討します。
- 中小企業でポストが限られていても、「配置転換の可能性を検討した」というプロセス自体が、解雇回避努力として重要になります。
- 退職勧奨(合意退職の打診)
- 配置転換も困難な場合、最終手段である解雇の前に、従業員に退職を促す「退職勧奨」を行うことを検討します。
- これはあくまで合意による退職を目指す話し合いであり、強制ではありません。退職金の割増など、従業員にとってのメリットを提示し、自主的な退職を促します。
- 注意点: 大声で威圧したり、何度も執拗に面談を強要したりすると、違法な「退職強要」と判断されるリスクがあるため、冷静かつ慎重に進める必要があります。
STEP 4: 普通解雇の実行 – 法的に有効な手続き
上記すべてのステップを踏んでも問題が解決せず、会社として雇用契約の継続が困難であると判断した場合に、初めて「普通解雇」という最終手段を実行に移します。
- 解雇予告(労働基準法第20条)
- 原則として、
解雇する日の30日以上前に従業員へ予告する必要があります。
- 30日前に予告できない場合は、不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
- 解雇通知書の交付
- 解雇日と、解雇理由を具体的に記載した「解雇通知書」を作成し、本人に交付します。解雇理由は、STEP 1で記録した客観的な事実と一致している必要があります。
- 解雇理由証明書への対応
- 従業員から解雇理由の証明書を請求された場合、会社は遅滞なくこれを交付する義務があります(労働基準法第22条)。
STEP 5: リスク管理と紛争予防 – 会社を守るために
万が一、解雇が「不当」と判断された場合、企業は以下のような計り知れないリスクを負います。
- 金銭的リスク: 解雇期間中の給与(バックペイ)や慰謝料の支払い 31。
- 信用的リスク: 「従業員を大切にしない会社」という評判が広まり、受注や金融機関の評価に悪影響。
- 組織的リスク: 社内に残る従業員の士気低下や、人材採用難の深刻化。
このような事態を避けるため、日頃から以下の取り組みが重要です。
- 就業規則の整備: 解雇事由などを具体的かつ明確に定め、全従業員に周知する。
- 採用時のミスマッチ防止: 求めるスキルや業務内容を正確に伝え、ミスマッチを防ぐ。
- 公正な人事評価: 客観的な基準で評価を行い、定期的にフィードバックする。
結論:ロードマップを手に、まずは専門家へ相談を
ここまで見てきたように、建設現場の問題社員への対応、特に普通解雇は、段階的かつ慎重な手続きと客観的な証拠が不可欠です。
【普通解雇までのロードマップ要約】
- STEP 1: 問題行動を客観的な事実として記録する。
- STEP 2: 書面も活用し、段階的な指導・教育で改善の機会を与える。
- STEP 3: 配置転換を真剣に検討し、退職勧奨で合意退職の可能性を探る。
- STEP 4: 全ての手を尽くした上で、法的手続きに則り解雇を通知する。
- STEP 5: 日頃から紛争予防策を講じ、リスクを管理する。
このロードマップは、企業が踏むべき道のりの地図です。しかし、実際の道は複雑で、一つ手順を間違えるだけで大きな紛争に発展しかねません。
問題社員への対応に悩んだら、自己判断で進める前に、早い段階で労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談してください。それが、会社と従業員の双方にとって、最善の解決への一番の近道です。
免責事項・更新日 本記事は2025年7月1日時点の法令・業界動向に基づき作成しています。個別案件は事実関係により結論が異なります。最終判断は労務専門の弁護士へご相談ください。 執筆・監修:スマートリーガル法律事務所(弁護士 寺口飛鳥)