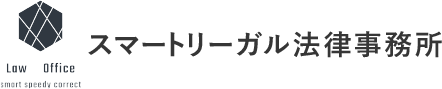2025/07/27 労務問題
【介護施設の経営者様へ】問題職員の解雇、法的に大丈夫?弁護士が教える普通解雇の進め方と紛争予防策
「何度指導しても、ケアの質が改善しない…」
「職員間のトラブルが多く、チームワークが乱れている…」
「利用者様やご家族からのクレームが特定の職員に集中している…」
介護・福祉の現場では、深刻な人材不足から「一人でも辞められると困る」という現実と、利用者の安全と尊厳を守るために「問題のある職員を放置できない」という高い倫理的要請との間で、多くの経営者様が日々苦悩されていることと存じます。
最終手段として職員の「普通解雇」を考えざるを得ない場面もあるかもしれません。しかし、その判断と手続きを誤れば、「不当解雇」として法的な紛争に発展し、事業所に多大な金銭的・信用的ダメージを与える可能性があります。
本記事では、スマートリーガル法律事務所が、介護・福祉業界の特殊性を踏まえ、問題職員への対応から普通解雇に至るまでの法的に正しい手順を「5つのステップ」で分かりやすく解説します。

STEP 1: 法的リスクを理解する – なぜ介護業界の解雇は難しいのか
まず大前提として、日本の法律では、会社が一方的に従業員を解雇することは厳しく制限されています。労働契約法第16条は、解雇が**「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」**であると認められない場合、その解雇は無効になると定めています。
簡単に言えば、解雇するには「誰が見ても納得できる理由があり、かつ解雇という手段がやりすぎではない」ことを、すべて会社側が証明しなければなりません。
特に介護業界では、
- 職員の行為が利用者の安全や尊厳を具体的にどう脅かしたのか
- チームケアにどのような支障を生じさせたのか
- 解雇を避けるために、施設としてあらゆる努力を尽くしたのか
といった点が、裁判所で厳しく問われます。このハードルを理解することが、すべての始まりです。
STEP 2: 問題の客観的な記録・証拠化 – すべての土台作り
「態度が悪い」「やる気がない」といった主観的な評価は、法的な証拠になりません。解雇の正当性を主張するための土台となるのは、客観的で具体的な事実の記録です。
【記録すべきことの基本原則】
「いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたか(5W1H)」を意識し、問題が発生した直後に、感情を交えず事実のみを記録します。
【介護現場で収集・作成すべき証拠の例】
- 公式な業務記録: 介護記録、事故報告書、ヒヤリハット報告書に、問題行動の事実を具体的に記載する。
- 指導・面談記録: 指導した日時、内容、職員の反応などを書面に残します。本人の署名があれば理想的ですが、拒否された場合はその旨を記録しておけば問題ありません。
- 第三者からの聴取記録: 他の職員や利用者・家族から話を聞いた場合は、その内容を記録します(プライバシーには最大限配慮)。
- 物的な証拠: 勤怠不良の場合はタイムカード、業務命令違反の場合は指示内容を記したメールなどが該当します。
STEP 3: 改善指導と教育機会の提供 – 解雇回避努力の実行
問題行動を記録したら、次は改善の機会を与えます。これは、職員のためであると同時に、会社が「解雇を回避するために努力した」ことを示すための極めて重要なステップです。
- 段階的な指導・警告を行う
- 口頭での注意・指導: まずは穏やかに、しかし具体的に問題点を指摘し、期待する行動を伝えます。この口頭注意も必ず記録に残しましょう。
- 書面による注意・警告: 改善が見られない場合、「業務改善指導書」や「警告書」を交付します。問題点、改善期限、そして改善されない場合は次の処分があり得ることを明記し、事態の重大さを伝えます。
- 具体的な教育・研修の機会を提供する
能力不足が問題であれば、OJTを強化したり、外部の専門研修(認知症ケア、コミュニケーション技術など)に参加させたりします。これらの研修に参加させた事実も、会社の支援努力を示す重要な証拠となります。
STEP 4: 配置転換の検討 – 「最後の手段」であることの証明
指導や教育を尽くしても改善が見られない場合でも、直ちに解雇に進むのは早計です。その前に、配置転換によって雇用を継続できないかを真剣に検討する義務があります。
【介護現場で検討し得る配置転換の例】
- 身体的負担の大きい業務から、レクリエーション担当や見守りが中心の業務へ変更する。
- 夜勤が負担になっている場合、日勤専従のポジションへ変更する。
- 介護業務への適性がないと判断される場合、施設内の事務、清掃、送迎などの非介護業務への異動を打診する。
たとえ施設内に適切な異動先がない場合でも、「配置転換の可能性を真剣に検討し、本人に打診した」というプロセスとその記録が、解雇がやむを得ない最終手段であったことを示す上で重要になります。
STEP 5: 最終手段としての「退職勧奨」と「解雇通知」
あらゆる手段を尽くしても問題が解決しない場合、最終的なステップに入ります。
- ① 退職勧奨の実施(紛争の軟着陸)
一方的な解雇通告の前に、合意による円満な退職を目指す「退職勧告」を実施します。これは、退職金の割増などの条件を提示し、あくまで従業員の自発的な退職を促す話し合いです。即決を迫らず、十分な検討期間を与えることが重要です。「辞めないと解雇する」といった威圧的な言動は、違法な「退職強要」と判断されるリスクがあるため、言動には細心の注意が必要です。 - ② 普通解雇の通知(法的手続きの完了)
退職勧告に応じない場合、最終手段として普通解雇の手続きに入ります。
- 解雇予告: 労働基準法に基づき、解雇日の30日以上前に「解雇予告通知書」を交付するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います。
- 解雇理由証明書: 従業員から請求された場合、会社は遅滞なく交付する義務があります。この証明書には、これまで記録してきた具体的な事実に基づき、解雇理由を網羅的に記載する必要があります。後から理由を追加することは困難なため、作成には専門家のアドバイスを求めることを強く推奨します。
まとめ:紛争予防と、やむを得ない場合の正しい対応
不当解雇をめぐる紛争は、事業所に多大なダメージを与えます。最も重要なのは、解雇という事態を避けるための日頃からの取り組みです。
- 採用時のミスマッチを防ぐ(仕事の厳しさも正直に伝える)。
- 就業規則を整備する(解雇事由を具体的に明記する)。
- 職員が成長できる研修制度を整える。
- 職員の心身の健康を守る仕組みを作る(相談窓口、メンタルヘルスケアなど)。
これらの予防策を講じることが、法的リスクを低減し、質の高い介護サービスにも繋がります。
それでも問題が起きてしまい、解雇を検討せざるを得ない場合は、本記事で解説したステップを一つひとつ着実に実行することが、あなたの事業所を守るための道筋となります。
しかし、個別の事案はそれぞれ複雑であり、自己判断は危険を伴います。対応に悩んだら、できるだけ早い段階で、私たちスマートリーガル法律事務所のような労働問題に精通した弁護士にご相談ください。それが、最も安全で確実な解決への近道です。