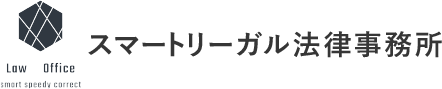2025/08/21 労務問題
【弁護士が3業界を徹底比較】建設・介護・タクシー、問題社員の普通解雇で共通する「7つの鉄則」
「何度指導しても安全意識が低い建設作業員」
「利用者への言葉遣いが不適切な介護職員」
「顧客からのクレームや事故が絶えないタクシードライバー」
建設、介護、タクシー。これら社会に不可欠なサービスを提供する3つの業界には、ある共通の悩みがあります。それは、深刻な人材不足という現実と、事業の根幹をなす「安全」や「品質」を確保するために問題のある従業員を放置できないというジレンマです。
この困難な状況下で「普通解雇」という選択肢が頭をよぎることもあるかもしれません。しかし、その判断と手続きを誤れば、「不当解雇」として法的な紛争に発展し、企業の存続を揺るがしかねません。
本記事では、スマートリーガル法律事務所が、これら3業界の事例を比較分析し、業種を問わず通用する、問題社員の普通解雇で失敗しないための「7つの鉄則」を解説します。

鉄則1:法的な「解雇の壁」の高さを知る
まず大前提として、日本の法律では、会社が従業員を解雇することは極めて厳しく制限されています。労働契約法第16条は、解雇が**「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」**という2つの要件を両方とも満たさなければ、権利の濫用として「無効」になると定めています。
- 客観的に合理的な理由: 誰が見ても「それなら解雇もやむを得ない」と納得できる正当な理由のことです。
- 社会通念上の相当性: その理由があったとしても、「解雇」という処分が重すぎないか、社会の常識に照らして妥当であるか、というバランスの問題です。
どちらか一方でも欠ければ、解雇は無効となり、会社は解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いや、従業員の復職を命じられるリスクを負います。
鉄則2:主観を捨て「客観的な証拠」で語る
解雇の有効性を主張する際、「態度が悪い」「やる気がない」といった経営者の主観的な評価は証拠になりません。必要なのは、具体的な行動や事実を示す「客観的な証拠」です。
- 【建設業なら】: 「高所作業時に安全帯を繰り返し不使用だった」という事実を、作業日報や安全パトロールの記録で証明します。
- 【介護業界なら】: 「利用者への不適切な言葉遣いがあった」という事実を、介護記録や他の職員・家族からの具体的な聴取記録で固めます。
- 【タクシー業界なら】: 「危険運転や営業の怠慢があった」という事実を、ドライブレコーダーの映像やGPSの走行データで客観的に示します。
鉄則3:いきなり「レッドカード」ではなく「イエローカード」から始める
裁判所は、会社が解雇という最終手段に至る前に、従業員に十分な改善の機会を与えたかを重視します。問題を発見して、いきなり解雇(レッドカード)を言い渡すのは極めて危険です。
まずは「イエローカード」にあたる、段階的な指導・勧告から始めなければなりません。
- 口頭での注意・指導: まずは具体的な問題行動を指摘し、改善を促します。この口頭注意も、日時や内容を記録しておくことが重要です。
- 書面による注意・警告: 改善が見られない場合、「指導書」や「改善勧告」といった書面を交付し、事態の重大さを認識させます。この書面には、改善すべき点、改善期限、そして改善されない場合の処分の可能性を明記します。
鉄則4:改善の「機会」と「支援」を提供する
指導するだけでなく、会社として改善のための具体的な支援を行うことも「解雇回避努力」の一環です。
- 【建設業なら】: 未熟な技能者に対して、経験豊富な職長によるOJT(現場教育)を計画的に実施したり、業務に必要な資格取得を支援したりします。
- 【介護業界なら】: コミュニケーションに課題がある職員に対し、専門の研修に参加させるといった機会を提供します。
- 【タクシー業界なら】: 売上が低いドライバーに対し、添乗指導を行って効率的な営業ルートを教える、売上の良いドライバーの考え方を学ばせるなどの具体的な教育を行います。
これらの支援を行った記録は、会社が真摯に改善努力を尽くしたことを示す有力な証拠となります。
鉄則5:「別の椅子」を探す努力を怠らない(配置転換の検討)
従業員が現在の職務に適応できない場合でも、会社は「解雇以外の方法で雇用を継続できないか」を真剣に検討する義務があります。その中心となるのが配置転換です。
- 【建設業なら】: 高度な技術が求められる現場から、比較的単純な作業が中心の現場への異動を検討します。
- 【介護業界なら】: 身体的負担の大きい業務から、レクリエーション担当や見守りが中心の業務へ変更したり、日勤専従のポジションへ変更したりします。
- 【タクシー業界なら】: ドライバー職から、内勤の配車係や点呼担当者といった職務への転換を提案します。
たとえ会社が小規模で配置転換先がない場合でも、「配置転換の可能性を検討した」というプロセスとその記録を残すこと自体が、法的に極めて重要です。
鉄則6:最後の説得「退職勧奨」を慎重に行う
あらゆる手を尽くしても改善が見られない場合、一方的な解雇通告の前に、話し合いによる円満な解決を目指す「退職勧奨」を検討します。
これは、あくまで従業員の自発的な退職を促す「お願い」「提案」です。退職金の割増などの条件を提示し、合意による退職を目指します。
注意点: 執拗に面談を繰り返したり、「辞めなければ解雇するぞ」といった威圧的な言動をとったりすると、違法な「退職強要」と判断され、損害賠償請求の対象となる可能性があります。必ず冷静に、相手に考える時間を与えながら進めましょう。
鉄則7:最終通告は「書面」で、理由を具体的に
退職勧奨にも応じず、やむを得ず最終手段として解雇に踏み切る場合は、法に定められた手続きを厳格に遵守しなければなりません。
- 解雇予告: 解雇日の30日前までに予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います。
- 解雇通知書・理由証明書: 解雇を通知する書面には、鉄則2で記録した客観的な事実に基づき、解雇理由を具体的かつ網羅的に記載する必要があります。後から理由を追加することは原則として認められないため、作成には細心の注意が必要です。
まとめ
建設、介護、タクシー。各業界が直面する問題はそれぞれ異なって見えますが、従業員の普通解雇をめぐる法的な課題と解決への道筋には、驚くほど多くの共通点があります。
今回ご紹介した「7つの鉄則」は、業種を問わず、会社を法的なリスクから守り、健全な労務管理を行うための普遍的な原則です。問題社員への対応は、場当たり的に行うのではなく、この鉄則に沿って、段階的かつ慎重に進めることが不可欠です。
しかし、実際の事案は一つとして同じものはありません。対応に悩んだら、自己判断で進めてしまう前に、早い段階で私たちスマートリーガル法律事務所のような労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。それが、会社と従業員の双方にとって、最善の解決への一番の近道です。