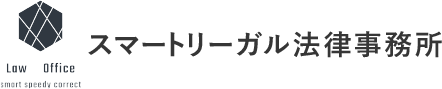2025/09/15 労務問題
【IT企業の経営者様向け】“問題社員”に退職してもらうための実践ロードマップ
テクノロジーの進化とリモートワークの定着により、IT企業を取り巻く環境は激しく変化しています。
その中で、経営者の悩みの種となりやすいのが「パフォーマンスが低い従業員への対応」です。
- スキルが陳腐化しており、プロジェクトに貢献できていない
- リモート勤務で仕事ぶりが見えず、成果も出ていない
- チーム開発なのに非協力的で、他メンバーに悪影響を及ぼしている
こうした「問題社員」を抱え続けることは、技術的負債の増大や優秀な人材の流出につながる現実的な経営リスクです。しかし、安易に解雇をすれば「不当解雇」として訴訟・労働審判に発展する可能性もあります。
そこで本記事では、普通解雇を検討せざるを得なくなったIT企業の経営者が、法律トラブルを避けながら適切に対応していくための実践的ステップを解説します。

Step1:IT業界における解雇の「法的ハードル」を理解する
日本の労働法では、従業員の解雇は非常に厳しく制限されており、労働契約法16条では「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が求められます。
わかりやすく言えば、「誰から見ても解雇に値する理由があり、なおかつ解雇という手段が妥当だ」と判断されなければ無効となります。
特にIT業界は、スキルの変化や勤務態度の判断が主観に寄りやすく、法的なハードルが高くなりがちな分野です。
- スキル不足:技術変化の速さゆえ、本人の努力不足か会社側の教育不足かの見極めが難しい
- リモート勤務:勤務状況の可視化が難しく、客観的評価が揃えにくい
したがって、感覚的・印象的な判断ではなく、「会社側が誠実に対応してきたこと」を証明できる客観的プロセスが求められます。
Step2:問題点を「証拠化」する – IT企業だからこその武器を活かす
解雇を正当化するためには、主観的な評価ではなく客観的な証拠が不可欠です。
IT企業の場合、日常業務で使っているツール群そのものが「法務ツール」になります。
- Git等のリポジトリ:コミット頻度、コード品質、レビュー履歴
- Redmine・Jira等のタスク管理ツール:チケット処理状況、見積工数との乖離
- Slack・Teams:勤務時間帯の応答履歴、他メンバーとのやり取り
- 1on1・面談議事録:指摘・指導内容を記録し、本人に共有した履歴
これらを日頃から収集し、「生産性が明らかに低い」「再三の指導にも改善しなかった」ことを記録しておくことが重要です。
Step3:改善機会(PIP)を提供する – 解雇回避努力の実践
法律上、解雇は「最後の手段」でなければなりません。
そこで、実務では「PIP(Performance Improvement Plan)」を導入し、改善機会を正式に与えることが望まれます。
PIPには以下の要件が求められます。
- SMARTな目標設定(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)
例:「3ヶ月で担当モジュールのバグ発生率を○%→○%以下へ」
- 書面交付+署名取得:目的・期間・未達時の対応(解雇検討)を明記
- 継続的な面談と指導:放置せず毎週1回程度フィードバック
PIPを誠実に実施することは、改善のチャンスを与えた=「解雇回避努力を尽くした」という強力な証明になります。
Step4:配置転換(リスキリング)の検討 – “別ポジション”の提案
たとえPIPでも改善しなかった場合でも、すぐに解雇には進めません。
次の選択肢として、社内の別ポジションで活躍可能かを検討する「配置転換義務」があります。
- 開発 → QAエンジニア(品質保証)
- 開発 → 社内ITサポート/ヘルプデスク
- 開発 → テクニカルライター/教育担当
「真剣に配置転換を検討したが適切なポストがなかった」という記録は、最終的な解雇の正当性を担保します。
Step5:最終手段としての退職勧奨・普通解雇
あらゆる手立てを尽くした後、どうしても改善が見込めない場合、ようやく「退職勧奨」「普通解雇」に進みます。
▼退職勧奨(ソフトランディング)
退職金増額等の条件を提示し、本人の合意に基づいて円満退職を促します。
即決を迫らず、威圧的な言動を避けることが重要です。
▼普通解雇
退職勧奨に応じない場合、普通解雇を実施。以下の手続きを踏む必要があります。
- 解雇予告:30日前に予告、又は30日分の平均賃金支給
- 解雇理由証明書:請求があれば遅滞なく交付(これまでの証拠を基に記載)
経営戦略としての「人材リスク管理」を
問題社員対応は単なる“人事課題”ではなく、企業の健全な成長を守るための経営判断です。
重要なのは、「問題が起きてから対処する」のではなく、
- 開発プロセスに目標管理・評価基準を組み込む
- 定期的な1on1で指導記録を積み上げる
- コードやチケットを評価の仕組みに活用する
といった“紛争が起きにくい設計”を、日常から組み込むことです。
「正しい対応」が会社を守ります。悩んだら弁護士へ
普通解雇を実行するには、段階的な手続きと証拠が不可欠です。「感覚的に問題があるから」「周りが迷惑しているから」だけでは、法的トラブルに発展する可能性があります。
もし、
- 対応に悩んでいる問題社員がいる
- PIPや配置転換など、どこまで実施すべきか判断に迷う
- 解雇を考えているがトラブルなく進められるか不安
という場合は、ぜひ早めにご相談ください。
スマートリーガル法律事務所では、IT・スタートアップ企業に特化した労働問題の解決実績を多数有しております。経営者様の“攻め”と“守り”の意思決定を、法務の側面から全力でサポートいたします。