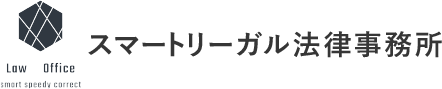2025/09/21 労務問題
【飲食店経営者様へ】問題社員の解雇、その前に。
弁護士が教えるトラブルにならない普通解雇の進め方
「人手が足りないのに、もうこれ以上は放っておけない…」
——不愛想な接客、衛生意識の低さ、繰り返されるミス。小さな飲食店にとって、一人の従業員の振る舞いが、お店の評判・売上すべてを左右します。
しかし、最終手段として“普通解雇”を選択する際は慎重の上にも慎重を要します。手続きや理由を誤れば、「不当解雇」として訴訟に発展し、慰謝料・未払賃金・SNSでの風評被害など、かえって大きなトラブルとなるリスクがあるためです。
本記事では、スマートリーガル法律事務所が、飲食業界特有の事情を踏まえた“問題社員対応から普通解雇までの正しい進め方”をステップ形式で分かりやすく解説いたします。

なぜ飲食店の「解雇」は難しいのか?
日本の法律では、従業員を解雇できるのは
- 客観的に合理的な理由
- 社会通念上の相当性
の2つを満たす場合に限られます。
しかも、それを証明する責任(立証責任)はすべて会社側が背負っています。
飲食店の場合は特に、
- 慢性的な人手不足・高離職率
- 接客ミスや衛生問題が“すぐSNSに晒される”
- ホールと厨房のチームワーク重視
という業界の特殊性から、裁判所も「解雇が本当にやむを得なかったのか?」を厳しく判断する傾向があります。つまり、“気に入らないから辞めさせる”は完全にアウト。段階的に、かつ手順に沿って“解雇の正当性”を積み上げていく必要があるのです。
解雇前に必ず踏むべき3つのステップ
STEP①:証拠を集める
“印象”ではなく“事実”で語れるようにする
|
主な記録 |
具体例 |
|
クレーム記録 |
日時・内容・対応結果をまとめた「クレーム報告書」 |
|
業務ミス記録 |
POS・オーダーシステムに残る入力ミス・処理ミスの履歴 |
|
指導記録 |
「〇月〇日、〇〇の件について注意。本人は反省すると回答」などのメモ |
|
勤怠記録 |
無断遅刻・欠勤の回数、シフト交換履歴など |
※おすすめは“日報・連絡ノート・面談メモ”による継続的なログ化です。
STEP②:改善の機会を与え、その記録を残す
“解雇を回避する努力”を示すことが法律上のキーポイント
- 段階的指導:口頭 → 書面注意(注意書・警告書)→ 戒告 とエスカレーション
- 数値目標の設定:「ミスを週2回→1回以下に」等、改善基準を明確に
- 研修・再教育:ロールプレイング・マニュアル再確認など
⚠ 裁判所は「改善を促したのに、それでも変わらなかった」というプロセスがあるかを見ています。
単に“能力が低い”“接客が悪い”だけでは解雇は認められません。
STEP③:配置転換など、解雇以外の手段を検討する
“最後のカードが解雇”であったことを証明する
- 接客が苦手 → キッチン補助へ
- 店舗Aでトラブル → 店舗Bへ異動
- 店長 → 一般従業員へ降格…等
たとえ小規模店舗で異動先がなかったとしても、
**「検討したが適当な部署はなかった」**という記録を残すこと自体が重要です。
最終手段としての解雇を実行する際は
- 退職勧奨(ソフトランディング):
解雇前に「〇月末退職であれば退職金加算」など提示して退職合意を目指す。
- 解雇通知:
就業規則に沿った“解雇理由”を明記した文書を交付し、30日前予告 or 解雇予告手当を支払う。
まとめ:解雇の命運を分けるのは「プロセス」です
飲食店の解雇トラブルのほとんどは、手続きの雑さ・記録不足・改善機会の欠如から起きています。
裏を返せば、“正しい手順”と“地道な証拠づくり”さえできていれば、訴訟になっても「正当な解雇」と認められる可能性は大いにあります。
忙しい現場でも、今日からできること——
・日報に指導内容を書く
・クレームを必ず記録する
・注意は“伝えっぱなし”にしない(サイン・メモを残す)
そして何より、判断に迷ったら早めに弁護士へご相談ください。
“問題社員への対処”は、結果として他の従業員とお店を守るための経営判断です。
スマートリーガル法律事務所では、飲食業の現場を理解した上で、解雇リスクを最小限に抑える方法をご提案しています。お気軽にご相談ください。